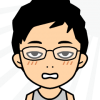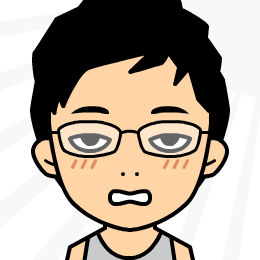どもども~(^^)v
「宿根セリンセ」と呼ばれているかどうかわかりませんが、
それに該当するのが多年性のこちらのセリンセ・グラブラ(Cerinthe glabra)だと思います。
季節によって葉の枚数が減ったりしますが、基本的にほぼ常緑です。
花色は黄色で開かないというのか尖っています。
ここでは一年草のセリンセ・マヨールとの違いと比べながら育て方や性質をまとめました。
画像とデータ

咲いている状態。
- 学名:Cerinthe glabra
- 別名:
- 分類:ムラサキ科
- 原産:欧州、コーカサス地方
- 形態:耐寒性多年草
- 耐寒性:USDA 7b(-15℃前後)
- 花期:通年
僕が育ててるこのグラブラがどの種類にあたるかわかりませんが、いくつか亜種(ssp.)があると言われています。
分布地域が欧州でも内陸部の中欧を中心に、北欧や欧州側地中海沿岸、ちょっと離れて黒海沿岸部となっているようなので距離的なことが亜種を生んだのかなっと勝手に想像してます。
草丈は30cm、株張りも30cmほどを目安にしてください。

二年目でもこの程度の草丈です。
マヨールよりかなり小さいです。
スポンサーリンク
育て方

小さい花です。
セリンセ・グラブラですが注意することは、この一点に尽きます。
ココに注意
最高気温が一時的に40℃近くまで上がる時期でも屋根も何もない屋外に置いておいても問題なかったですが、水はけがそれほど良くない土に植えた株や若い株は枯れました。
「何と比べて」と言われてると応じずらいですが、鉢植えで育てる場合は植える土にゼオライト(多孔質鉱物)を2割ほど入れて水はけを良くし、根が呼吸できるようにする工夫をされた方が良いかなと思います。
庭植えや地植えの場合は平面な場所ではなく、雨水や水やりした水が滞留せず流れていく角度がある場所が良いかと思います。
かと言って水やりは自然雨のみの「常に乾燥している場所」ような場所ですと水切れを起こし枯れます。ネペタやサルビア、グラスの類しか育たないような場所では育てられません。
もちろん冬の間でも水分が原因の根腐れは起こるのでご注意を。
耐寒性は問題ない気温なのに植物が枯れる原因を考えてみた。原因は寒さではない可能性が高いです。
耐寒性

寒いのは割かし平気。
屋根のような遮るものがまったくない完全な屋外放置にて耐寒温度がどのくらいかを観察しましたが、
屋外放置した年の冬が暖冬ということもあり最低温度が-4℃まで下がった日が一日あっただけで、
それほど参考になる温度ではないですが-4℃程度でしたら葉に痛みも入らずまったく問題なく越冬します。
分布している一部の地域の気候帯では-25℃程度まで下がることがあるので、かなり寒さには強いと思います。
耐暑性

水切れするものの蒸れて枯れる株も。
セリンセ・グラブラは寒さよりも暑さ、それも高温多湿の環境に気を付けた方が良いです。
参考までに2018年よりも気温は低かったものの、酷暑と言われた2019年の夏を当地(愛知県西部)を越えられた株は20ポット中で10ポットです。
個人的には半分は夏越しできたので「まぁまぁかな」っという感想です。
それと常緑とは言え、
ココに注意
株がボロボロになりながら夏越しします。
分布地域の多くは気温は上がっても関東以西の暖地の夏のような80%を超える湿度はありません。
分布地の一つである黒海沿岸部は欧州に比べ湿度が高い地域ですが、それでも高くてもせいぜい70%です。
それらの地域の最高気温は40℃を超えることがありますが、湿度は日本と比べると低いため「ヌメっ」とした暑さではなくかなり乾燥してます。
そのような地域が原産地なため色々な植物と密植したり、風が当たらず空気の流れがない中心部に植えるとすぐに枯れます。

この状態から復活する場合もあります。
水はけやそれほど高くない草丈などを念頭に入れると花壇でしたら手前が良いかと思います。
水やり
根腐れを起こすとは言え、基本的に常緑なため水切れします。
夏の間の水やりに少しコツが必要です。葉がしおれたら水やりを行う感じです。
重複しますが植える土にゼオライトを混ぜておけば水やりの頻度が多くても根腐れのリスクは抑えられます。
植物の水やりについて。時間は夜が良いの?「土の表面が乾いたら」するのが正解なの?頻度など実例を。
性質
マヨールとの違い
葉

大きめの葉が横に展開します。
セリンセ・グラブラの葉ですが、マヨールと比べると一枚の葉が大きくセリンセ特有の葉に入る白い模様が少ないです。
実生した数十の苗を見比べましたが、だいたいどの苗も同じくらいの斑点の量でした。
花期

つぼみ。開花直前。
花期の通年についてですが、1年強観察してみて
メモ
- 株が充実していて
- 最高気温が25℃以上ある
という状態でしたら咲いています。
原種だからか多少肥料が切れていても咲いてます。
実際に温室内でずっと管理している株は1月でも2月でも咲いていて、ずっと屋外に放置してある株は10月の下旬に咲いた後は3月になってもつぼみすら確認できていません。

屋外株は3月中旬になりつぼみが。
一年草のセリンセ・マヨールは基本的に「日が長くならないと咲かない長日植物」なので、太陽が上がっている時間が短い真冬にはたとえ暖かい施設に入れたとしても咲きません。
-

-
セリンセ・マヨール の育て方について。冬越し方法を。肥料食いなのでしっかりやりましょう!
続きを見る
というわけで今日はセリンセ・グラブラでした~
ではでは~(^^)v