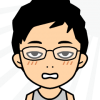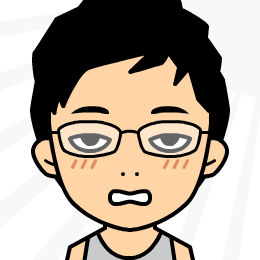どもども~(^^)v
初夏から開花する日本原産の多年草のシキンカラマツ(学名は Thalictrum rochebrunianum 読み方はタリクトラム・ロケブルニアヌム)の育て方についてです。
「山野草」として扱われていますが、近年は庭植えやガーデニング花材として植えられる人が増えている印象があります。
「山野草」と聞くと寒さには強いものの高温多湿に弱いモノが多く、扱いずらい印象を持っている人は決して少なくないと思いますが、
このシキンカラマツは案外高温多湿の環境に強く、関東以西の太平洋側の暖地と呼ばれる地域でも夏越しを容易にします。
ですが数点だけ気を付けてください。
画像とデータ

つぼみが丸く可愛らしい。
- 学名:Thalictrum rochebrunianum
- 別名:シキンカラマツ
- 分類:キンポウゲ科
- 原産:日本(長野県など)
- 形態:耐寒性多年草
- 耐寒性:USDA 4(-28℃前後)
- 花期:初夏
長野県、群馬県、福島県の山間部に分布しています。
本州のごくごく一部の分布です。
草丈は160cm、株張りは60cmを目安にしてください。
植え替えなどを行い一年以上様子を見てみて、なんとなく3.5号サイズのポット苗から草丈が160cm以上の完成形になるのには2~3年は必要かなと思います。
スポンサーリンク
特徴
見分け方

固く太い茎です。
オオシキンカラマツと呼ばれるタリクトラム・デラバイ(Thalictrum deravayi)という画像だけ見るとシキンカラマツとほぼほぼ同じに見え、
あるあるな悩み
一体どっちがどっち・・・?
と困惑してしまうと思います。
学名はまったく違いますが和名は似ていますしね。
それでオオシキンカラマツとシキンカラマツの決定的な違いは
ココがポイント
シキンカラマツは花茎が固く太いです。強い風が吹いても折れそうにないくらいしっかりしています。
わかりやすい見極めのポイントは花でも葉でもなく茎です。

株が大きくなると花茎も多く上がります。
他には
参考
- 葉の大きさが違う
- 開花時期がシキンカラマツの方がオオシキンカラマツよりもちょっと遅い
- オオシキンカラマツの原産地は中国
- シベの長さ
など違いはありますが、「シキンカラマツは花茎がしっかりしている」というのを覚えておくと簡単に見分けられます。
育て方

Photo credit: westher on Visualhunt.com
シキンカラマツはお庭で新たに開花するモノが少なくなる7月の中旬以降から開花を始め、
比較的明るくない半日陰のような場所を好むため国内外のガーデナーにとって重宝されています。
つぼみがピンク色で丸いのでそれも画になり可愛らしいのも良いですね。
耐暑性

開花後は株のボリュームが減ります。9月の様子。
分布が長野県や群馬県の山林という涼しめの環境でありながらも、関東以西の太平洋側の暖地と呼ばれる高温多湿の地域でも夏越しします。
色んな植物が生い茂る場所でも腐ってドロドロになることがなく、案外密植えや混植えにも耐えることができます。
花が咲き終わると一度葉や花茎の大部分が汚くなり枯れ始めますが、
枯れながらも地中から新しい茎が伸びて来て新しい葉が現れ涼しい秋に生育します。
意外に華奢に見えますが、水やりを忘れて水切れさせない限りは枯死することはないような気がします。そこそこ強いです。
ただし気を付けた方が良い点はあります。
直射日光には長く当たらない方が良い状態を保てます

明らかに葉色が悪いです。
直射日光に当たるのが悪い訳ではないですが、少なくとも良いとは言えません。

肥料切れや黄金葉ではなく直射日光に長く当たり色が変わっただけです。
大きな木で光が遮られていて日光がまばら程度しか当たるような場所に自生している植物は葉色(緑色)が濃い場合が多いです。
少ない日光で光合成を行うために葉の色を濃くしてそこで生きています。
そんな葉の色が濃い植物を長時間直射日光に当てると、当然ながら葉焼けしたり葉の色が薄くなります。最悪枯れます。
この記事内のシキンカラマツは365日直射日光が1日4~6時間は当たる場所で管理していたため、葉の色が薄くなり黄色っぽくなってしまっています。
シキンカラマツの自生地は間違いなく夏の熱を帯びた直射日光が数時間も当たらない場所であろうと思いますので、
庭植えや地植えをされる際は半日陰程度の暗さの場所を選んで植えるのをおすすめします。
この植物に限った事では無いですが、葉色が薄いよりは濃い方が健全な状態です。
画像のように葉が黄色くなり直射日光が当たっていた場合は、植えた場所がシキンカラマツにとっては明るすぎたと判断してください。
耐寒性

最高気温が15℃を超える時期になるとワラワラと新しい葉が現れます。
耐寒性については何も心配することはないでしょう。
寒さが決定的な原因で枯れ死することはないと思って良いです。
もし冬越しできなかったら、寒さではなく根が
地上部分をほぼ枯らし葉も茎も残さず越冬します。
最高気温が15℃を超える時期になると徐々に地中から新しい芽が伸びてきて、新しい青々とした葉が次々と現れます。

花びらに見えるのはガクで反るように開く。
というわけで今日はシキンカラマツ(タリクトラム・ロケブルニアヌム) でした~
ではでは~(^^)v