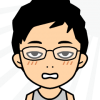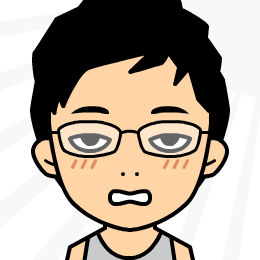どもども~(^^)
バンクシア・ブレクニフォリア(Banksia blechnifolia)は、オーストラリア南西部に分布する匍匐性のバンクシアです。
低木で横に広がる形状をしており、地面に沿うように生育します。
バンクシア特有の花姿とヒトツバのように地面から立ち上がっているように見える樹形が魅力で、植物好きの間で少し話題になった種類のバンクシアです。
場合によっては「土の中から生えて来ている」ように見える花の咲き方も独特です。
夏に雨が少なく湿度がほとんどない、という日本の夏と真逆の地中海性気候の地域に自生していますが割と育てやすいです。
もちろん鉢です。地植えは自己責任で行なってくださいね。
本文のデータや写真等はすべて筆者自身の観察によるものです。
画像とデータ
- 学名:Banksia blechnifolia
- 別名:グランドカバーバンクシア
- 分類:ヤマモガシ科
- 原産:オーストラリア(西部)
- 形態:常緑樹
- 耐寒性:USDA 10b(0℃前後)
- 花期:春
分布地域はオーストラリアの西オーストラリア州(WA)と呼ばれる州の一部、南西オーストラリアと呼ばれる地域です。
誰か
西オーストラリア州は本場の地中海よりもはっきりとした地中海性気候帯
と呼ばれるくらいはっきりとした地中海性気候、らしいです。
西オーストラリア州の地中海性気候について簡単に言いますと、
- 夏はほぼ雨が降らない
- 夏の最高気温は30℃以上で湿度は低い(40%以下)
- 冬は雨がたくさん降る
- 冬の最低気温はせいぜい-3℃程度で湿度は高め(70%前後)
というものです。
この気候を認識しておくとこの植物の攻略方法がけっこう容易になるかなと思います。
またこのバンクシアの原産地域は「世界有数の生物多様性ホットスポットの一つ」と呼ばれ、8000種を越える植物の中で少なくとも47%は固有種とされている地域と言われています。
植物多様性の密度においてバンクシア・ブレクニフォリアの原産地域は、南アフリカのケープ地方を上回ると書いている論文もあるくらいです。
種小名の「ブレクニフォリア(blechnifolia)」ですがシダの1種で「ブレクナム」というモノがありまして、その葉に似ているからということで命名されています。
ただどのブレクナムの葉と似ているとは断定されていないようで、バンクシア・ブレクニフォリアは国内でよく流通しているシルバーレディと呼ばれるブレクナムでは葉の形がまったく似ていないのでこれではないでしょう。
樹高は訳70cm、株張りは1mを目安に。
英名(グランドカバーバンクシア)と呼ばれる通りに上に伸びず、横に幹を伸ばして行きます。
分布域や樹高などは下記サイトを参考にしました。
スポンサーリンク
バンクシア・ブレクニフォリア 育て方の基本|日当たり・水やり・土など
日当たり
日当たりは1日6時間は直射日光が当たる場所が望ましい──・・・
ですが当圃場では6月から10月まで遮光率3割ほどの遮光ネットを温室全体に張っていまして、
その下で3年育てていますがまったく徒長していないので、案外直射日光の強光線は必要ないのかなっという感触があります。
たまに直射日光が当たり常時半日陰以上の明るさの場所なら良いのかなと思います。
水やり
バンクシア・グランディスに代表されるように西オーストラリアに分布している植物を国内で育てる場合に、もっとも多いであろう枯らす原因である「水やり」。
下記に記しましたが、このバンクシアは水はけが良い、排水性に優れた土に植えておけば根腐れは他の西オーストラリア原産の植物と比べると格段に少ないです。
鉢植えで育てることになると思いますが、水やりのタイミングは基本中の基本ですが
見出し(全角15文字)
- 鉢の表面の土が乾いて
- 鉢を持ち「明らかに軽いな」と感じ
- 葉が少ししおれたら
このタイミングがベストです。
2までの段階で水やりを行なっても良いです。
1だと表面は乾いていても鉢の内部の土は水分がある状態で、この時に水やりすると根腐れするかもしれませんので注意してください。
それと水やりですが、
土に向けてやってください。株全体にかけると痛み株が弱ることがあります。
このバンクシアに限ったことではないですが、日本で流通しているオーストラリア原産の植物は日本よりも年間雨量が少ない地域に自生しているモノが多いです。
そのため株全体を濡らすように水やりを行うと、葉が落ちる・葉色が悪くなるなどの生育不良を起こすことが多いです(特に鉢植え管理の株)。
こういった理由で水やりは土に向けて水を垂らしてくださいね。
水やりについてはこちらの記事を。
土
土については2点のみ。
ココに注意
- 肥料分がまったくない土
- 水はけがめちゃめちゃ良い土
これは絶対です。この2点は枯らさずうまく育てるのに必須です。
1の肥料分のない土について、理由はヤマモガシ科のためリン酸をよく吸い上げるプロテオイド根です。そのため痩せた土に植えてください。
続いて水はけの良い土について。
・大粒赤玉土5:山野草の土5
・大粒赤玉土3:中粒日向土4:パーライト3
といった、感じでとにかく水はけ重視の配合で。
配合がめんどくさい人はパーライトやゼオライトが入っている山野草の土と中粒日向土を半分づつ混ぜたモノでも良いです。
とにかく「排水性が良く肥料分が皆無な土」を作って植えてください。
すでに何度も書いていますがこのバンクシアは西オーストラリアに分布している割と根腐れしにくいです。と言うのかバンクシア・インテグリフォリアなど育てやすい他の種類のバンクシアと同じような土で良いです。
バンクシアの間違いない育て方。高温多湿と寒さに優れている4品種を。(プロテオイド根についての説明があります)
バンクシア・ブレクニフォリアの耐暑性と夏越しのポイント
西オーストラリアに分布している植物の多くの日本の高温で高湿度の環境が「超」苦手です。
というのも地中海性気候帯の夏は30℃以上になっても湿度は40%を越えることはほぼないです。というかたぶん20%以下の日もあると思います。
わかりやすいところで湿度40%というと関東以西の太平洋側の温暖な地域ですとだいたい12~2月ごろの「気温が低くても洗濯物が乾く」時期です。
バンクシア・ブレクニフォリアはこのような「湿度が低い乾いた夏」の下で自生しています。
ただ、バンクシア・ブレクニフォリアについては割と高温(35℃以上)で高湿度(70~80%)が長期間続く環境下でも耐えます。
最高気温が35℃以上の酷暑日が47日あった2024年の愛知県西部地方の夏を「温室の中」で何の問題もなく夏越ししています。
雨ざらしにしない限りは大きな問題が出ずに夏越しするな、という印象です。
それでも年中屋外管理が出来、地植えも可能な「育てやすい」種類のバンクシア・ロブルなどよりは、雨が当たらない場所に移動させるなど、の注意は必要です。
バンクシア・ブレクニフォリアの耐寒性は?冬越し対策と注意点
こちら、まだ屋外で放置は行なってません。
耐寒温度について、霜・雪・寒風除けできる無加温温室内での話ですが氷点下になっても葉にはまったく痛みが出ず、「単なる低温」でしたら-3℃程度までならまったく問題ないのかなという感じがします。
軽い霜やすぐに溶ける雪程度なら枯れずに耐えると思いますが、ブルーデージー(フェリシア・アモイデス)のように雪は一発アウトで枯れるというのモノもあるので枯らすのが心配な人は軒下に置くなり簡単な防寒をした方が無難だと思います。
バンクシア・ブレクニフォリアの花について
花が地面から生えている理由
他の植物には少ない「土から花が飛び出ている奇抜な見た目」というのがもっとも印象的なこのバンクシアですが、
実は決して「花が土から生えている」訳ではありません。
下のこちらの画像を見ると一目瞭然です。
英名の「グランドカバーバンクシア」の名の通りに、樹にしては少ない枝を「ほぼ真横の方向に」向けて伸ばします。
そして数少ない枝はけっこう地面に近い位置に沿って伸びていきます。
地面と近い位置を横に伸びるため、風や雨などの影響を受け土や枯れ葉でその枝は埋もれやすいです。
その埋もれた枝の先から花が上がってくるので、結果的に「花が地中から生えている」ように見えます。
自生地の南西オーストラリアの環境はおそらく風がよく吹き、土が軽く冬の雨で流されやすいんだと推測してます。
僕もこの生育の仕方がわかるまで地面から花が飛び出て来ると思っていましたが、土などに花芽になる枝が埋れただけです。
そこそこの年数が経過し大きく育った株は高い位置(それでも地面から40cmとかのですが)からでも枝を出し地面すれすれでない地点で開花することもありますが、この植物の性質なのか花は地面スレスレの枝の方に多くつくようです。
鉢植えの場合は土などに埋もれることがないので、上のような感じの地面を張っているような枝と地面から現れているように見える花の生育状況が見られます。
つぼみを確認してから開花までは約2ヶ月強を要します。
というわけで今日はバンクシア・ブレクニフォリアでした~
ではでは~(^^)v